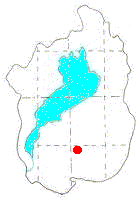1.はじめに 知らない土地に行くと珍しい名前に出会うことがあります。 その土地の歴史や風俗を連想させてくれるもの、意味が連想できないもの、 読み方が想像を絶するもの、などに出会うと、旅の楽しみが増します。 私の住んでいる土地の近くにも興味深い地名がありますので、いくつか取 り上げてみました。 下図のように、JR野洲駅から日野町の綿向神社(わたむきじんじゃ)まで、 自動車で行く時の交差点の標識を確認したものです。2.地名あれこれ 2.1 小篠原(こしのはら:野洲市)
JR野洲駅の南にある国道8号線を少し東に走ると、 「小篠原」に出ます。 この国道8号線は、昭和30年代に作られたそうです。 交差点のすぐ近くに野洲中学校があり、その左手奥に 福林寺跡磨崖仏 が 鎮座しています。
←近江八幡に向かう ↓正面に野洲中学校(8号線の南側)
2.2 大篠原(おおしのはら:野洲市)
小篠原の少し東に「大篠原」があります。 JR篠原駅と野洲駅の中間位の位置です。 JR篠原駅は野洲駅と近江八幡駅の間にあります。 「篠原」という地名は、篠竹が沢山自生していたことによるもの、だろうと 推測しています。私は篠原地区の篠竹を採って篠笛を作っています。 かつて篠原地区で採れたもち米で作った餅は、鏡餅の元祖とされているそ うです。ここ「大篠原」に近い国宝・大笹原神社の本殿横には、篠原餅の神 を祀る「餅の宮」があります。 「大篠原」交差点から程遠くない所で陶芸用の「篠原土(しのはらつち)」 が産出されています。陶芸によく使われる白い粘土の高級品です。
←近江八幡に向かう ↓正面奥に大笹原神社(8号線の南側)
2.3 鏡口(かがみぐち:竜王町)
野洲市から竜王町に入った辺りが「鏡」という地区です。 鏡という名称の由来は知りません。 「鏡口」交差点の手前、左側に、8号線に面して鏡神社があります。 この神社の祭神は「天日槍(あめのひぼこ)」です。天日槍は新羅の王子で、 製陶技術を伝えたそうです。万葉集に登場している額田王(ぬかたのおおき み)はこの地の出身だそうです。 義経元服の池、平家終焉の地もこの近くです。
←近江八幡に向かう ↓後方に鏡山
2.4 弓削(ゆげ:竜王町)
近江八幡市に入り、右手(南側)に折れて日野川を渡 ると「弓削」交差点があります。 竜王町は室町時代に近代弓術(吉田流)が確立した地だそうです。 「弓削」という名称はそれに因むものだろうと思います。「弓始め神事」と 「弓納め神事」が今でも石部神社で行われています。 ここを少し(南へ)下ると、左手(東)に雪野山があり、その麓に万葉の 時代を偲ぶ「妹背の里」があります。
←日野川の堤防が背後にある弓削 ↓日野町に向かう(正面に雪野山)
2.5 葛巻(かずらまき:東近江市)
苗村神社を右に見てから東名高速をくぐり、左に進む と「葛巻」交差点があります。旧蒲生町です。 葛巻の名称の由来は知りません。 近くの日野川で葛が採れて、それを加工した品が評判になったのでしょうか。 ここを右に折れて南下せずに真っ直ぐ東に進むと、石塔寺に行けます。
←葛巻交差点 ↓
2.6 蒲生堂(がもうどう:東近江市)
葛巻から少し南下すると「蒲生堂」交差点があります。 田んぼの中の交差点です。旧蒲生町です。 蒲生の語を見ると、万葉集の相聞歌が思い浮かびます。 額田王が歌を詠んだ 蒲生野 とはどの辺りなのでしょうか。今回この記事 を書いてみようと思ったきっかけのひとつは、この「蒲生堂」を見たことで した。
←後方に雪野山 ↓日野町に向かう
2.7 鈴(すず:東近江市)
蒲生堂からさらに南下すると、「鈴」交差点がありま す。 鈴の名称の由来は何でしょうか。ロマンを感じさせる名前です。 つい最近交差点の一角にコンビニができましたが、人家のない場所です。 人家がない、というのは現在の(多分、最近整備された)自動車用道路の交 差点のことで、「鈴」の地名はかつての街道筋の集落に付けられたのでしょ う。
←鈴交差点 ↓日野町に向かう(前方に綿向山)
2.8 鋳物師(いものし:東近江市)
日野川を東に渡ると「鋳物師」交差点があります。 鋳物師とは、その名の通りの職人が多数住んでいた土地なのでしょう。 標識には「いものし」とローマ字で表記されていますが、「いもじ」と読む のが正解だ、という記事を読んだことがあります。 鋳物師という地名は全国各地に散在するようです。私が信楽へ通う途中の 道路わきにも「鋳物師」という石碑が建っています(栗東市辻)。
←鋳物師交差点 ↓日野町に向かう
2.9 三十坪(みそつ:日野町)
日野町の市街地の手前にあります。 ここを初めて訪れた人が「三十坪」を「みそつ」と読むのは至難でしょう。 名前の由来は、よく分かりませんが、昔の土地の広さを表す単位なのかも知 れません。 綿向神社へは左折しますが、右折して少し進むと、「芋くらべ祭」が行わ れる中山地区があります。
←三十坪交差点 ↓綿向山が近づいてきました
3.綿向神社
日野町役場を右に見ながら走る と間もなく綿向神社です。 前方に綿向山(1,110m)が 大きく見えてきました。 ←綿向山(正面中央、手前の森が 綿向神社) 綿向神社(馬見岡綿向神社:うまみおかわたむきじんじゃ)は市街地の外 れにあります。毎年5月に行われる「日野祭」には、16基の曳山が綿向神 社に勢揃いするそうです。
←森に囲まれた綿向神社 ↓境内に設けられた土俵
.jpg)
←(左)入口・(右)出口の札 ↓石橋を渡って拝殿へ
この神社は、財を築いた 日野商人 たちからの寄進が多かった様子が感 じられます。
←休憩所(1階) ↓本殿
綿向神社は、綿向山々頂に祠を建てた(欽明天皇6年:西暦545年)の が始りで、その後(延暦15年:西暦796年)里宮として今の地に祀られ たそうです。山頂の神社(奥之宮=大嵩神社:おおだけじんじゃ)は古来か ら20年毎に社殿を建て替える式年遷宮の祭事が、今も続けられているそう です。もっとも、インターネットで確認した限りでは、大嵩神社は鳥居と小 さな祠だけのようです。 4.おわりに 今回取り上げた地名は、その由来を詳しく調べたわけではありません。 おいしい近江牛を味わえるレストランが綿向神社の手前にあります。そこへ 時折通っているうちに興味が湧いたものを取り上げてみただけです。 竜王町には、今回のコースから少し外れた位置に、「薬師」、「須恵」、 「川守」、「綾戸」などの興味深い地名があります。 綿向神社の近くで地元(多分)の若者4人に(4人一緒ではなく、一人ず つ)質問してみました。 ・綿向山とはどの山か? ⇒4人がほぼ一致(どちらの峰か、について断定したのは1人だけ) ・山頂に神社があることを知っているか? ⇒知っている、と答えたのは1人 ・山頂にあるという「大嵩神社」はどう読むのか? ⇒答えたのは0人 30歳前後の若者に、地元の歴史や史跡などを質問するのは不適切なのだ ろうか。 (散策:2009年9月9日) (脱稿:2009年9月29日) ご参考: ・JR野洲駅の近くにある磨崖仏 ⇒ 野洲の磨崖仏 ・国宝大笹原神社と鏡餅 ⇒ つれずれ日記 No.61 ・源義経ゆかりの地 ⇒ 義経元服の地と平家終焉の地 ・蒲生野など、万葉集ゆかりの地 ⇒ 妹背の里 ・日本最古の石造三重塔 ⇒ 石塔寺 ・天下の奇祭 ⇒ 芋くらべ祭 ・日野祭と日野商人館 ⇒ つれずれ日記 No.46 ・日野商人ゆかりの木地師 ⇒ 木地師の里 ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ 報告書メニューへ トップページへ